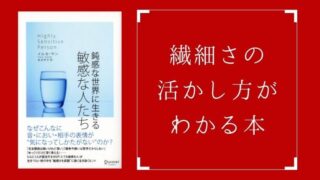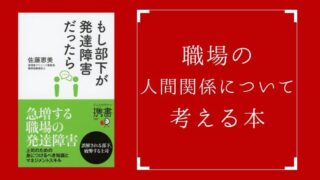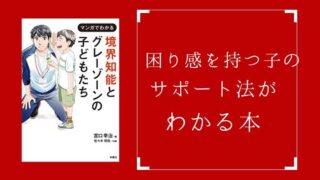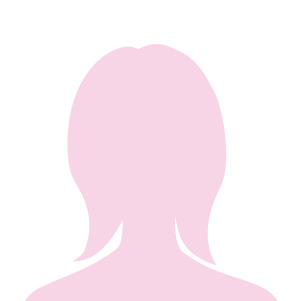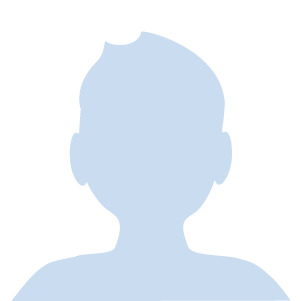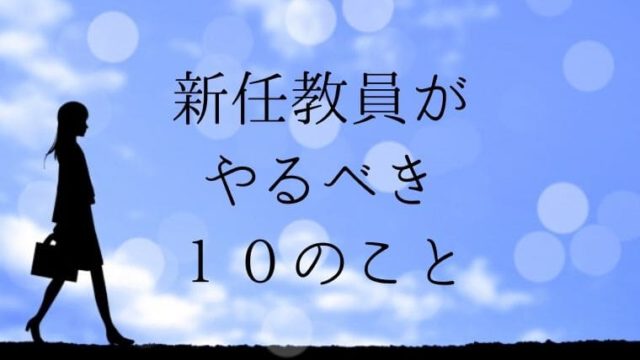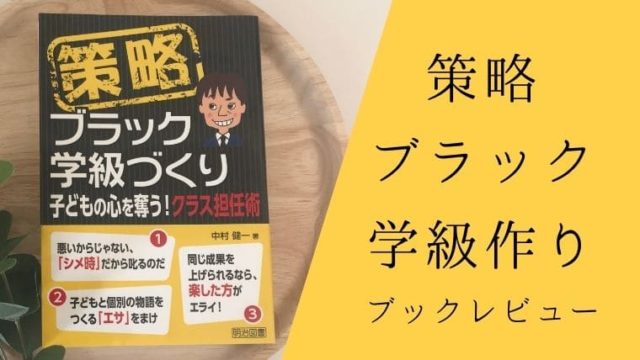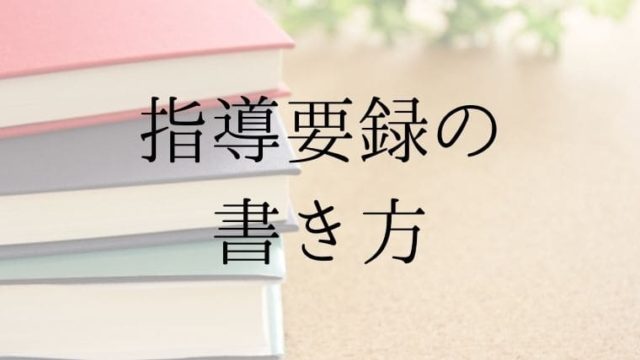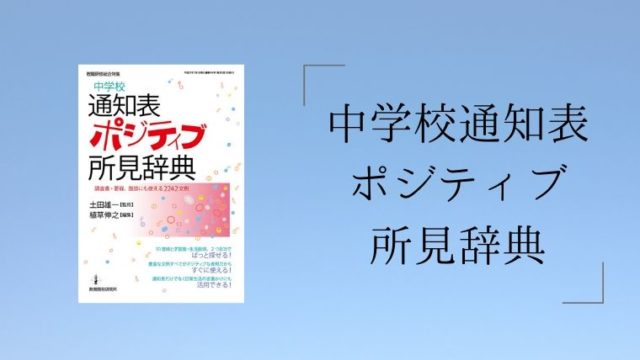本を読みたいけれど、時間がない!気力が残ってない!
と感じている先生はいませんか?
学校の先生は、平日は夜遅くまで仕事があり、本を読む余裕はありませんよね。
土日も部活があったり、持ち帰り仕事もあったりと、なにかと忙しい。
土日がまるまる休みだったとしても、買い物をしたり、たまっていた家事をこなしていたら、もう日曜の夜…。
本好きの方でも、本を買うだけで満足してしまい、積読本が増えていく…ということは「あるある」ではないでしょうか。
息抜きに見るものと言えば、もっぱらスマホ。
息抜きはもちろん必要だけれど、もう少し「ためになる」息抜きの仕方があったら、嬉しいですよね。
そんなあなたにオススメなのが、Amazonが提供する書籍朗読サービス「オーディブル」です。
「オーディブル」には、なんと12万以上もの作品があります。
日本一読まれている自己啓発書、「夢をかなえるゾウ」↓
特別支援教育のエキスパート・小嶋悠紀さんと、ADHD特性を持つ息子さんとの日々を発信する漫画家・かなしろにゃんこ。さんの著書「発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全」↓
(2024/04/25 15:25:59時点 Amazon調べ-詳細)
Twitterフォロワー数8万人超えの特別支援学校の先生・平熱さんの「特別支援教育が教えてくれた 発達が気になる子の育て方」↓
刊行10周年を迎えた、アドラー心理学の世界的ベスト&ロングセラーの「嫌われる勇気」↓
俳優の高橋一生さんが朗読している、村上春樹の小説「騎士団長殺し」↓
お笑い芸人・オードリー若林正恭さんと、サトミツこと佐藤光春さんのトーク番組『佐藤と若林の3600』↓
これらの本はすべて、オーディブルで読めます。
そんなオーディブルですが、わたしは最初「本を耳で聞いて、内容が記憶に残るのかな?」「読みたい本はオーディブルにはないかも」と、半信半疑でした。
しかし、30日間無料で試せるということで、モノは試しに会員登録。
結論から言うと、耳での読書、ちゃんと記憶に残ります!
家事をしながらの「聴く読書」は時間を有効に使えるし、読み放題なので紙の本を買うよりお得です。
今回の記事では
- 学校の先生にオーディブルがおすすめな理由
- 学校の先生にオススメのオーディブル作品
- オーディブルの登録&解約方法
について解説します。
- スマホで本の朗読が聴ける
- 有名俳優や声優が朗読しているので聞きやすい
- 教育書・自己啓発本・小説などラインナップ豊富
- 30日間無料で試せる(その後は月額1500円)
- 無料期間中に解約OK
- 何冊でも読み放題
目次
Amazonオーディブルが学校の先生にオススメな理由
スマホで本が聞ける
オーディブルを聴くには、つぎのいずれかの機器が必要です。
- スマートフォン
- タブレット
- PC
- Alexa(アレクサ)
いちばん手軽なのは、スマートフォンでしょう。
オーディブルのアプリをダウンロードするだけで、すぐに聞くことができます。
アプリはiOS版とAndroid版、どちらもあります。
いままでの読書は、当然ながら本を持って読まなければいけませんでした。
しかし、オーディブルは、何かをしながら読書することができるのです。
- 家事をしながら聴く
- 車や電車での移動中に聴く
- 散歩やランニングをしながら聴く
- 寝る前の布団の中で聴く
スマホとワイヤレスイヤホンを繋いだら「ながら読書」できるのが、オーディブルの長所です。

本のタイトルが豊富
芥川賞
直木賞
芸能人が朗読している本がある
高橋一生:『騎士団長殺し』シリーズ(村上春樹)
大森南朋:『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド(上・下)』(村上春樹)
妻夫木聡:『ノルウェイの森』(村上春樹)
千葉雄大:『幸せへのセンサー』(吉本ばなな)
松坂桃李:『サラバ!(上・中・下)』(西加奈子)
杏:『犬にきいてみろ』池井戸潤、『1Q84』シリーズ(村上春樹)
榮倉奈々:『Nのために』(湊かなえ)
上白石萌音:『君の名は。Another Side:Earthbound』(加納新太・新海誠)
大久保佳代子:『コンビニ人間』(村田沙耶香)
玉城ティナ:『推し、燃ゆ。』宇佐美りん
石田衣良:『娼年』(石田衣良)
芸能人のトークチャンネルがある
Journey to the origin with Anne(杏)
Amazonオーディブルで読める!学校の先生に読んでほしい本
1 ケーキの切れない非行少年たち
(2024/04/25 15:26:02時点 Amazon調べ-詳細)
著者:宮口浩治(児童精神科医)
再生時間:
引用:扶桑社ホームページ
2 特別支援教育が教えてくれた 発達が気になる子の育て方
著者:
再生時間:
引用:ホームページ
3 やめる時間術 24時間を自由に使えないすべての人へ
著者:
再生時間:
引用:ホームページ
4 「畳み人」という選択 「本当にやりたいこと」ができるようになる働き方の教科書
著者:
再生時間:
引用:ホームページ
5 ジェイソン流お金の増やし方
著者:
再生時間:
引用:ホームページ
(2024/04/26 02:48:54時点 Amazon調べ-詳細)
Amazonオーディブルの登録の仕方
Amazonオーディブルの疑問
登録は時間がかかる?
登録にはクレジットカードは必要?
オーディブルはいつ引き落とし?月末?登録日?
本当はお金がかかるんじゃない?
オーディブルの退会方法は?
退会したら、本は聞けなくなる?
Amazonオーディブルは忙しくても学びたい、学校の先生にオススメ!
- スマホで本の朗読が聴ける
- 有名俳優や声優が朗読しているので聞きやすい
- 教育書・自己啓発本・小説などラインナップ豊富
- 30日間無料で試せる(その後は月額1500円)
- 無料期間中に解約OK
- 何冊でも読み放題